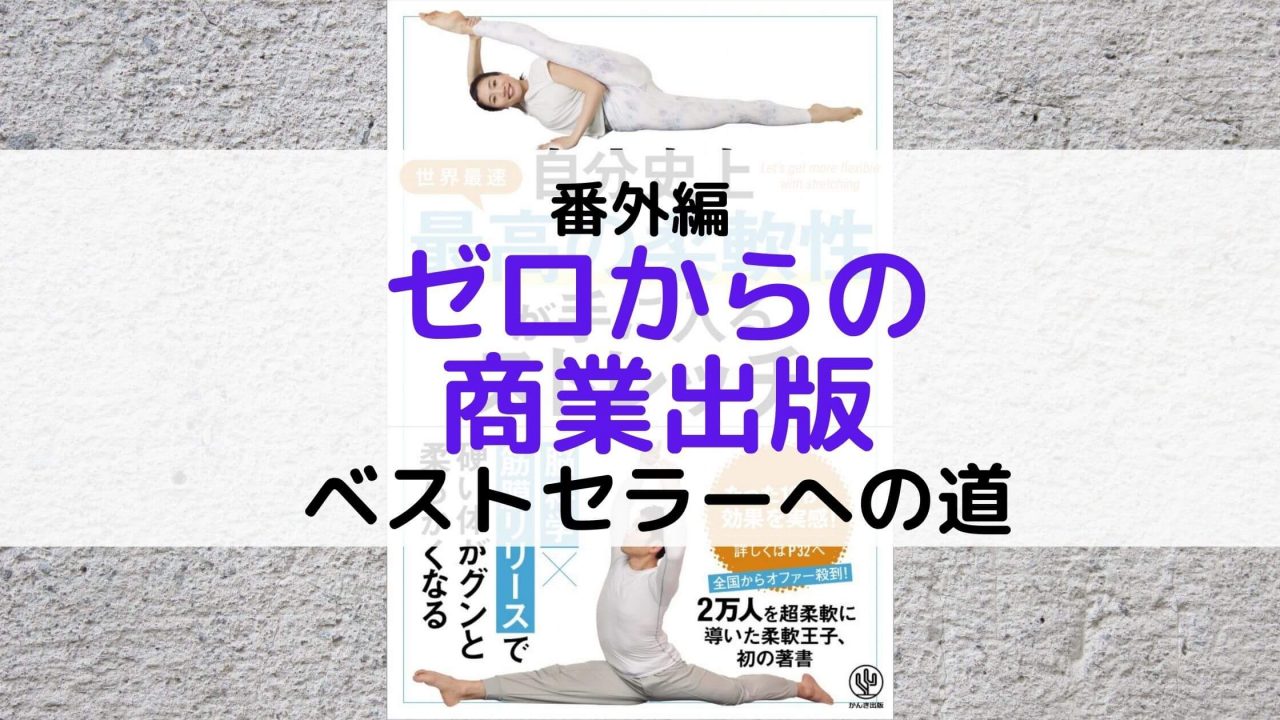公開日2020/7/20 最終更新日2021/11/13
本稿はスポーツ本、奇跡のベストセラー「自分史上最高の柔軟性が手に入るストレッチ」の誕生秘話です。
本を出してみたい、本を出し有名になりたい、という人に役立つかも知れない、勇気が出る体験記です。
番外編:出版界の常識を覆したゼロからのベストセラー、奇跡の執筆奮闘記
出版界の人脈ゼロから独力で商業出版にこぎつけ、2019-2020年のスポーツ本ベストセラーとなった「自分史上最高の柔軟性が手に入るストレッチ」(かんき出版)。
出版に至るまでの軌跡・思い出などの備忘録ですが商業出版にトライする方の参考になれば幸いです。
ただし、初めに断っておくと、あなたがよほどのネット有名人でもない限り、コネなし・出版実績なしの飛び込みで自己流の企画を提案しても採択される割合は軽く1%以下の狭き門です。
知名度ないところから商業出版に至るだけでも十分奇跡ではありますが、毎年5-6万点以上といわれる膨大な数の新刊書籍の中でさらに本書をベストセラーに仕立てあげたストーリーはまさに出版界の非常識であり、奇跡というにふさわしいのです。
ま、それでも私自身がそれを実現したわけですから無理ではありません。
というより、いびつな出版界の特性を知って正しく行動すれば、勝てる可能性は飛躍的に上がると感じています。
[headline style=”5″ align=”left” headline_tag=”h2″]その瞬間、私の中で出版企画がまとまった
[/headline]
私は高校生の時にほんのちょっと器械体操部に所属していた頃から180度開脚ができたし、ストレッチにはまあ自信があって、趣味レベルでストレッチを教えることもあった。
2018年4月、当時通っていたバレエ教室で本書の著者になっている村山巧氏のストレッチセミナーの存在を知る事になった。
半信半疑で参加した私だったが、体験してみて、本質はPNFと筋膜リリースの組み合わせだとすぐに悟った。
セミナーを受けながら、そういえばPNFを前面に出した書籍ってほぼ存在しないような気がするし、筋膜リリースは高齢者向けの腰痛改善というスタンスの書籍しか見たことが無い。。。
簡単で、速効性があり、再現性も高い、、、これなら本になる!この男を柔軟王子の名前で売り出そう!とひらめいた。
偶然だが村山氏とは自宅が割と近いこともあり、本を出してはどうかと持ち掛け、勝手に企画書を書くことにした。
[headline style=”5″ align=”left” headline_tag=”h2″]出版企画書を作成・出版社へ送ってみる
[/headline]
セミナー直後、2018年5月頃から出版企画書を作成した。
とはいえ、こちらも本当に出版に漕ぎつけるのかについては半信半疑だし、出版について教えてくれる人がいるわけでもなく遅々として進まず、後で考えればここで半年の無駄が生じてしまった。
出版コンサルタントと言われる職業の人がいることは知っていたが、タダってわけにもいかないし、まずは自力でということで、インターネットで「出版企画書の書き方」なんてものを調べながら制作を始めた。
村山氏に一部を書くように依頼するも残念ながら要領を得ず、結局、自力ですべて制作することとなった。
通常、企画書は2~3ページ、多くても5ページ程度が相場ということなので分量自体は大したことは無いが、要点を抑えることが極めて重要。
簡単に挙げれば
1ページ目で惹きつけられるか(=ちゃんと目を通してもらえる)
類書が多いか(=市場があるということ)
類書と何が違うのか(=斬新な切り口)
著者の業界での知名度や実績(=販売部数が見込めるか)
こういったあたりがキーポイント。出版実績が無いところから出版に漕ぎ着けるにはかなり尖った、というかキラリと光る要素が必須だ。
せっかくなら東大の人脈をたどろうとも考えたが、出版社の知り合いなど皆無。。。
でもなかったが、文藝春秋の記者では足しにならないので結局ゼロベースからの出発となった。
村山氏は自分の自己紹介すらまともに書けない、私とて出版に見識のある知人もない、という訳で半年近く、私一人でだらだらと推敲を重ねてきた。
しかし、年末も近づいてきた2018年11月、このままではいけないと考え、いよいよ本気モード。一人で勝手に走り出した。
改めて企画書の体裁を整え、過去にストレッチとか筋トレの本を出している出版社を調べてリストにし、計95社(100を目指したけど力尽きた)の編集部宛てに企画書を勝手にA4封筒で郵送した。運動ジャンルの本を出版した実績があるなら高い確率で乗ってくるだろうとの思いだった。
我ながらよくできた企画書だし、5社くらいは反応があるだろう!
で、その中で条件交渉して出版社を選べばいいや。
出版界の実情を知らない私は一人で勝手に盛り上がっていた(後で書くが、出版業界の実情を知っていたら本を書いてみようなんて思わなかったかもしれない。全くもって知らぬが仏とはこのことだ)。
2週間たったころ、ある大手出版社から郵送で返事が届いた。
待ってました!と開封するも「残念ながら見送らせて頂きます」というお断りの通知。それが5件ほど続く。
ちなみに、出版社には膨大な持ち込み企画書が届くため、返事すらくれないのが普通。
わざわざ断りの返事をくれるだけでも良心的な会社であり、基本的に無視されるのが当たり前である。
プロの出版コンサルタント(実体はブローカーに近いと感じるのだが)を介して提案先の出版社を厳選しても打率は1割未満と聞いていたので、出版に関してはド素人である私の企画書がそう簡単に採用されないであろうことは想定の範囲内だった。
とはいえ、発案から半年、時間をかけて何度も推敲して知力を結集し、全力で作り上げた企画書である。こう言っちゃなんだが、格が違うだろ、出版社同士で取り合いになるんじゃないかってな思いも当然あった。
それだけに全滅は心が折れる体験だった。後から編集者さんに言われたところでは、コネなし・出版実績なし・飛び込み企画提案で採択される確率は1%未満だそうだ(ま、1%は控えめな数字で実際には限りなくゼロに近く、20年編集者をやって見たことが無い、とのことだった)。
話をもどそう。
3週間ほど経過して全滅だと悟った私は、ダメでもともと、とばかりにインターネットで持込企画受け入れを表明している出版社を調べ、追加で3社に改めて企画書を送った。最後の悪あがきであった。せっかくだから、あと5社追加して計100社に送りたかったが調べ疲れてしまった。
音沙汰がないまま、さらに約3週間が経ち、「これは料金を払ってコンサル業者に任せるしかないな」と考え始めたころ、1通のメールが届いた。
かんき出版編集部Sさんより一度話を聞きたい、との連絡だった。
今でも送付先出版社のリストを残しているのだが、かんき出版は98社目に名前を挙げた、まさに最後の1通だった。
[headline style=”5″ align=”left” headline_tag=”h2″]企画会議を通過・商業出版確定!
[/headline]
まずは第一関門突破だが、ここからが本当の勝負(っていうか、本当の勝負がこのあとずーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーっと続くことになるとは思いもよらなかった)。
出版社内の企画会議に出してもらって、OKをもらわなければならないのだ。
2018年12月19日、年の瀬が迫ったタイミングで編集部のSさんと初対面。
まずはSさん自身にこのノウハウを気に入ってもらわなければ始まらない、ということで半ば強引に足裏ほぐしを体験してもらい、効果を実感していただくことにした。足裏は大変凝っている部位なので、ここをほぐすことで速攻で柔軟レベルが変わるのだ。作戦は奏功、喜んでもらえた。
しかし、私の企画案には異論がある感じだった。
編集者視点からの意見としては、「方向性は良いが、企画会議にかけるにあたり、もっと尖った感じにしたい」との由。
100万部「パカッーと開脚」をはじめ、横開脚の本は割とたくさんあるので、その中にあって実績ない著者で本を売るには十分に奇をてらうというか、目新しさが必要、という考えなのだった。
前後開脚をテーマにして企画書を修正して欲しい、「一日10分、一か月で前後開脚できるプログラム」を作って欲しいという依頼だった。。。
つまり、「誰でも1週間で前後開脚できちゃう!」本にしてくれというリクエストだった。
正直これは困った。いくらなんでも無理筋だ、と。10年バレエをやってても開脚できない人はゴロゴロいるわけで無理に決まってる。
大げさに煽る内容で本にしたところで「実際にそんな効果がない」とあとで酷評されるのが目に見えているじゃないか、と。。。
打ち合わせ後、私からの確認メールはこんな感じ。
『「中上級者向け、全身の柔軟アップ」という方針で企画書作成しましたが、今回は「一般読者向け、誰でも前後開脚できる!」に方針転換して企画書を修正するということでよろしいでしょうか』
本意ではないが、編集者の意図に沿わない限り出版はないわけで、ここは折れるしかないという判断があった。
出版社内での企画会議は月二回、1月は新年早々の2019年1月9日と聞いた。
ここは一気に勝負を決めたい私は勝手にスピードアップ。面談の翌日には企画書を書き換え、速攻で再度送った。
年明けになり、Sさんより企画会議の結果、大筋でOKが出たとの連絡があった。さらに社内会議の結果、一部方針を変更。
・メインの対象読者を「30~50代女性」から「アンダーアスリート(一般人でも割と本気でスポーツに取り組んでいる層、くらいの意味)」に
・書店では「健康の棚」ではなく「スポーツの棚」に置くイメージの内容にする
・「前後開脚」ではなく「ストレッチ全般」を前面に打ち出す
・参考の類書を想定し、「簡単」で「すぐ効果が出る」ことを強調
・美容面や健康面だけでなく、スポーツの効果を謳う
ということで改めて方針が変更され、「初級から上級まで対象、全身の柔軟アップ」で行くことになる。
結局、当初の私の企画案に戻った感じだ。
再度企画書を提出、めでたく合格となった。
よし、商業出版決定!
とはいえ、当時の私には、ここからさらに大変になる事など知るべくもなかった。。。
[headline style=”5″ align=”left” headline_tag=”h2″]台割り・ラフ作成
[/headline]
2月5日、出版決定後、初の打ち合わせ。なにしろ出版は初めてだから知らないことが盛り沢山、というか知らないことばかり。
台割り、ラフ、撮影、原稿という大まかなフローをご教示頂いた。
最初にやることは台割り作成。
台割りとは全160ページとして各ページの内容を項目だけ一覧表にするというもの。本の設計図であり、とりあえずの目次といったところ。
今回の例で言えば、2章・3章が主になるのだけれど部位をどのように分けるのか、それぞれ何ページ割り当てるのか、どんな応用ポーズを取り上げるのか、モニターページを冒頭に入れよう、コラムはどこに入れるか、その内容はどうする、など大まかな計画を立てる。
もっとも、具体的な内容が全然決まらない状態なので全くの暫定版で後々の変更は当然に生じる。しかし、これをやっておくことで、全体の流れ・どこに重点を置くのかというようなことが明確になり、分量も100ページじゃ足りないなとか200ページも書くことがなさそうだ、などといったことが決まってくる。
ちなみに普通の本は4枚重ねの紙が二つ折りで8枚16ページがベースとなっていて、それを集めてできているとこの時、初めて知った。だから本は概ね16の倍数ページで作られている(もちろんページ番号をどう振るかは別問題)。なので普通の単行本だと通常、144・160・176・192・208・224ページみたいな選択になる。
そのため、もし2ページ増やすのならあと14ページ分も追加で内容を考える必要が出てくる、ということになる。
今回はわかりやすく160ページで決定。台割は2月中に作成することとなった。
次にラフ作成。期限は3月末。
ラフとは台割りをもとに、各ページのおおよその構成を決めていくおおまかな原稿・下書きのこと。この辺にこんなポーズの写真があって、こんな説明があって、とか台割りをもとにさらに具体化していく。デザインの段階で大幅に変わるのでこの段階ではレイアウトとか色とかにこだわる必要はあまり無い、と後で判明。
ラフの書式は自由と言われたため、MicrosoftWordで作り始めたり、寄り道を随分しながらいろいろやって結果、仕事で使い慣れたパワポでラフを作成。編集者からはパワポでラフを作った人初めてだと言われたが、写真メインの本はPowerPointが作業しやすいはずだ。
言葉だけでコチラにこんなポーズの写真、アチラにあんなポーズの写真ということだと他の人にはピンとこないので、自分の写メやらネット画像やらを並べてイメージを具体化していく。
さらにモデルは誰にする?モニターさんは?各ページの内容は?カメラマンは誰?決めることは山盛りだ。
できれば知り合いに頼んでお金かけずにやりたい。
男女モデルの本なので、女モデルは私が通うバレエ教室の先生みきちゃんでいくとして、男モデルは俺が自らやると主張するも、編集者さんは若い人がいいという考えで平行線が続いた。最後は押し切って自ら登場することとなった。
俺が出ないと、自身は全くのゴーストライターになってしまうわけで俺が売る理由が無くなってしまうのだから、これは重要な分岐点だったといえる。
ちなみに出版社の編集者は制作にあたり全面的な裁量をもっているので、こちらの希望の進路に誘導することはあまり難しくない。何しろ、編集者さんは同時並行で数冊の書籍制作を手掛けているわけだから忙しいわけです。そこへ、カメラマン・イラストレーターを私が連れてきて日程調整も報酬の交渉も済んでるとなれば、基本的に断る理由がなくなります。
本書でもカメラマン・挿絵・メイク担当を私の知り合いで固めることに成功した。
彼ら自身の宣伝になる面もあるわけだから、結果、これも奏功した。
ということで、企画・執筆・モデルを私が担うことになった。
実際には、内容は99.9%私の整理なので私自信が著者を名乗りたかったが、形式上、著者の名前はストレッチ界の知名度がある村山氏で、ということに決まった。
商業出版はあくまで出版社がコスト・リスクを背負うわけで出版社の考えが最優先となるのでこの点は致し方ない。
4月中に撮影、6月に原稿完成、本の発売は最短で7-8月くらいというざっくりしたスケジュールが決定。
ハッキリ言ってこの時点では、写真メインで動きやポーズに関する簡単な説明が大半なんだから原稿作成は簡単に終わると思っていたのだった。。。
[headline style=”5″ align=”left” headline_tag=”h2″]写真撮影
[/headline]
2019年4月3日、ラフ原稿ができたところで打ち合わせ。
3週間後の4月21日に撮影日が決まった。カメラマンは特に決まってないというので知人を紹介した。数年、ビジネス交流会に出ていると大抵の業種に知人がいるので結局、カメラマンだけでなく、メイク担当、挿絵のイラスト担当も知人をあてがってもらった。
なにしろ、大きなコストはかけられない。会場代もいらないところがいいということで、バレエ教室だの公民館だのと案は出たが結局、コストはかかるものの、きれいな白い壁がある撮影専門スタジオに落ち着いた。
体験モニター7名、年齢・性別・運動経験バラバラでギリギリになってかき集めた。高齢者モデルを1人くらい入れたいということで私の母まで動員することとなった。
なお、本書の特長のひとつとしてパステル調の明るい紙面が挙げられる。
衣装は私もみきちゃんも白ベースとなっている。
もともと、くっきりはっきりするから赤とか黒とか派手目な衣装が良いのでは?と思っていたんだが、編集Sさんの意向で白基調となった。
結論から言うと、類書と比べてこの明るい紙面が潜在意識レベルで心地よさを演出しているのだと私は感じている。
撮影までには、25ページの上にこんなポーズの写真、右にはこんなポーズ、という感じで細かなとこまで決まっている必要があるわけだから、撮影前に概ね内容が確定している必要がある。原稿をどんどん埋めていき、準備を進めた。
4月21日、青山のレンタルスタジオに朝8時集合。
思った以上にスタジオは狭くてモニターさんが7人もやってきたらパンパン。
無論、準備はしていったものの、私自身がモデルもやりながら、撮影の指揮もやる、という体制だったので思ったより時間がかかった。
結論から言うと300ポーズ以上の写真を撮るには5時間では全然足りなくて時間切れ終了。
平成から令和に変わったゴールデンウィーク、10連休の長い休みの間に、膨大な写真の中からどれを採用するかを選ぶ作業に追われ、連休後、補足の撮影が決まった。
[headline style=”5″ align=”left” headline_tag=”h2″]原稿作成本格化
[/headline]
撮影が終わると原稿作成が本格スタートした。
まずはベースとなるデザイン(見開き2ページ)をして頂くことになった。なのでそこの部分の原稿だけでも完成レベルの原稿にする必要がある。
ちょうどこのころ、パカッと開く特殊な製本技術であるコデックス装のことを印刷会社の社長から教わり、出版社には本件にぜひ採用してほしいと進言した。
コデックス装となると製本コストは高いし、製本に時間もかかるのだが、「脚も本もパカッと開脚」私の中では勝手にキャッチフレーズも出来上がった。
思い返せば、コデックス採用はここがギリギリのタイミングであった。発刊後、予想通りコデックスが高く評価されたことを考えればこれまた大きな分岐点であった。
後日お会いした他の出版社の方からは、50年も書籍製作に関わってきたけどこんなスゴいアイデアは初めて見たと言われた。ちなみに本書以降、コデックスのストレッチ本がポンポン出ている。出版業界は、2匹目のどじょう狙いがデフォルト戦略なのだ。
これまでは写真撮影に間に合わせるために、写真のレイアウトやポーズをどうするかが主眼だったので、説明などはおざなりに考えていたのだが、わかりやすい表現を考えて細部まで文字を見直す。文字ばかりのページもいくつかあるので文章ページもおおむね固める必要がある。たとえ数ページであってもしっかり書こうと思うと時間はかかる。
こういうときは類書を参考にするのがやはり早い。
流れを真似たり、表現方法を参考にしたり、アイデアを見るため執筆に当たっては、近所の図書館2つを掛け持ちして、借りた本はチラ見で終わったものも含めれば50冊をゆうに超える(100冊も超えてると思う)。
5月21日、仮デザインが届いた。ポップな感じとちょっとマジな感じの2種類。編集者さんと話した結果、両者の中間っぽくいくことになった。基本、デザインに関しては一応意見を聞いてもらえるものの出版社にゆだねるのが商業出版における暗黙のルールだ。
本らしくなってきたのでこちらも俄然スピードアップする。動きの説明や細かな表現とかどんどん埋めていく駆け込み作業が続き、できたページから順次デザイナーに送付する。
予定通り、5月末に一応全ページの原稿が完成した。
普通、初物の著者が予定通りに原稿を用意できることは少ないようだが、ここは相当頑張った。
[headline style=”5″ align=”left” headline_tag=”h2″]ああ、果てしない校正作業
[/headline]
一旦完成と同じタイミングですでに提出した原稿のデザインが上がってきた。ここからは校正に入る。
校正とは、誤字脱字の修正、です・ますを整える、わかりやすい表現に改める、といった作業。
やってみてわかるのは、これらは比較的簡単というか気づきやすい。読んで違和感があるから。
一番厄介なのは表記ゆれの統一だ。例えば「ひざ」「膝」「ヒザ」を「ひざ」に統一するというもの。個々の文は読んで意味が通じるので、よほど意識してみていかないとスルーしてしまう可能性が極めて高い。例えば半角英数字と全角英数字が混同していることに気づいたのはかなり終盤だった。
なお、校閲と校正という言葉がある。校正は上述のように形式面のチェックを指し、校閲はウソが無いか、矛盾が無いかという内容面のチェックにかかわるものを指すようだ。
校正は大変手間がかかる作業で今はPCで全文検索が簡単にできてしまうけれど、以前は大変だったろうな、というかどうやってたんだろう。
この作業は大変な割には付加価値があまりないわけなので、これこそAIで自動化されるべき仕事と強く感じた。
参考までに今回の校正で表記統一した用語の例としてこんなものがある。
原稿の表記→→→統一後
ひざ・膝・ヒザ→→→ ひざ
ひじ・ヒジ →→→ひじ
かかと、カカト →→→かかと
もも・太もも・モモ →→→もも
体側・体側部→→→ 体側部
本書・この本 →→→本書
体・カラダ・身体 →→→体
ページ、頁、P→→→ P
一人、1人→→→ 1人
是非、ぜひ →→→是非
もも前、ももの前面、ももの前側・前もも、もも前面 →→→もも前面
もも裏、ももの裏面、ももの裏側、もも裏面 →→→もも裏面
掴(む・んで)、つかむ →→→つか
この校正作業は単純作業で疲れるので、このプロセスにおいては形式著者の村山氏からも協力を得た。
実のところ、本書の製作にあたり、彼が手伝ったのはこの校正作業のみである。
話をもどそう。
表現を改めたり、字句を統一したりと修正を赤字で手書きし、送り返すというキャッチボールが続く。
はじめは1週間おきだった原稿のキャッチボールはだんだんペースが上がり、2日以内に返信、さらに翌日までに返信、という具合に急かされていく。
そして締切直前には6時間以内に返して!みたいなことになるのだ。
原稿の制作に取り組み始めて丸4ヶ月、企画書に着手してから考えれば、1年の戦いについに終止符を打った!
あとは本になるのを待つのみとなる。
ところが、、、意外な?事実が判明。
なんと、本は出して終わりじゃない。やっと戦いが終わったと思いきや、実は本当の戦いはこれからだったというロールプレイングゲームの裏面突入みたいな話。
そうです。本を書いただけで売れなきゃ自己満足、マスターベーション、紙の無駄で環境破壊になるだけ、まるっきり疲れるだけなのだ。
こうして「やっと終わった!」と思った俺の役割、実は全然終わってなくて、これから営業大作戦に移行することになる。
[headline style=”5″ align=”left” headline_tag=”h2″]類書に大差をつけた営業戦略
[/headline]
出版不況の現在、本を何冊も出しているメンタリストDaigo、堀江貴文、中田敦彦、池上彰といった超有名人の本でも10万部超えは本当に数えるほどしかない。
登録者ウン十万人のYouTuberの本だって同じく、出版社の目論見はことごとく外れ、大ヒットになるものはごくわずかである。
それに対して、こちらはメディア出演ゼロ、村山氏のインスタグラムフォロワーがせいぜい5,000人というレベルだから認知度・影響力という面では彼らの足元にも及ばない(足の小指の爪くらいか)。
にも拘わらず、本書は無名のところから超有名人を差し置いて15万部発刊(2021年11月現在)にこぎつけたのだ。
実は、ちゃんと理由があって、彼らがやらない営業戦略を私が徹底的にやったからこそなのである。
ここのところ、くわしくは別のブログに書きます。
[headline style=”5″ align=”left” headline_tag=”h2″]ベストセラーを生み出すのは難しいか?
[/headline]
電車とか雑誌とかの広告でよく、「7万部達成!」「10万部達成!」といった表示を目にしますが、これってスゴいんでしょうか?
100万部は誰でもスゴそうだと思うけれど、おそらく普通の人は10万部がスゴいなんて感覚はおそらくもってない。
特に40-50代以降の人は、昔「100万部」っていうキャッチコピーを新聞やらテレビやらで、よく目にしていたので、それが基準になってるようなフシがある。
だから10万部って大したことないな、と感じる人だっているはずなのだ。
じつは私自身、かなり甘く見ていた。本を出せばどんな本でも最低でも5万部くらいは売れるんだろう、ならば印税は〇〇万円、、、と思ってプロジェクトはスタートしたのだ。
はじめっから業界事情を知っていたら私の無謀なチャレンジはそもそもあり得なかったかも知れないわけで、無知が生んだ奇跡のベストセラーなのだ。
実際のところ、何冊くらい売れればヒット作と言えるのだろうか。
そもそも、たくさん売れることを想定していない学術書のような書籍もあるのでジャンルごとに異なるが、一般向けの本としては1万部あたりがヒット作、3万部なら大ヒット作というのかおおむね出版業界でのコンセンサスになっている。
意外に少ないと感じた方も多いだろう。ちなみにこれは2020年時点での感覚。
10年前なら3万部でヒット、5万部で大ヒットということだったようだからこの基準値は今後ますます基準値は下がっていくだろう。
さて、「本の年鑑」 (日外アソシエーツ)によりますと、2019年1年間の新刊はざっと52,000種類。
それぞれの発刊数は公表されているわけではないが出版業界の人の現場感覚だと、驚くべきことにそのうち、重版にたどり着くのは2割にも満たないという。
一般に初版は概ね3,000~5,000部になることが多く、重版とは初版の品切れが見えてきて追加で増刷することをいう。
つまり、ほとんどの本は出ただけで5,000冊も売れずに終わりだということ。
なお、よく売れている本なのかどうかは重版されているかが一つの目安ということなんだが、重版かどうかは本の後ろに第〇刷などと記載されているのでこれを見ればわかる。
ちなみに出版社としては初版が売りさばければ赤字にはならない、という計算でやっている。初版の製作にはデザイン費とか版代とかのコストがかかるのでかなり高いのだが、それを回収してしまえば、後のコストは印刷代だけで済むため、重版以降は利益率が高くなる。
そこで重版以降はお金を刷るみたいなもんだ、というのが出版社の考えである。むろん、全部の書籍が重版になるつもりで作製はスタートするのだが、期待に反してほとんどは重版に届かないのが実情なのだ。
さて、インターネット普及が始まって以来、大抵のことはネットで調べれられるようになっているし、ご丁寧に自分で本を読まなくていいように要約して解説してくれるYouTube番組も少なくない。
そうとなれば本を買うまでもないということで書籍の市場はどんどん小さくなっている。
私自身、本はまず図書館で借りて今後もずっと手元に置いておきたいものだけを買うというスタイルでいる。一回読めば済むような本は図書館で済ませればよく、買う必要が無いという考えだ。
さらに、
①書籍と言っても、電子媒体が隆盛となってきて紙媒体の書籍市場自体が小さくなっている
②個人がメルカリやらラクマやらで中古本を売りやすくなった。昔なら古本屋に持って行っても買取価格10円(もっと安いことも)!とか言われたわけで、なら持ってる方が良いやということになるところ、それなりの値段で売ることが可能になったのでわざわ新品でなくとも中古の本がネットで買いやすくなった。
ということで現在、ミリオンセラーは年間に数冊、という非常に狭き門である。ミリオンセラーまでいかずとも、10万部売れる本はごくごくわずかである。
年間5万種類の本のうち、ごくごく一部の書籍のみが10万部達成の称号を得ることができる。
その確率はざっと0.1%であろう。しかも10万部達成するのは常連の著作家とか芸能人・有名人が大半を占めると思われ、それ以外での10万部は相当のはハ-ドルだということになる。
翻って、本書籍は2020年春時点で15万部発刊である。冒頭で、たいして知名度のない状態でコネなし実績なしから出版にこぎつけるのはごくわずかであると述べた。さらにそれを15万部に押し上げた実績は控えめに言って出版業界の超奇跡なのである。
さて、よく聞かれる話なので印税について書いておこう。
巷で「夢の印税生活」なんて言ったりするけれど、上記からわかるように99.99%の本は夢のような生活とは程遠い結果に終わるのが現実だ。
お金の話をちょっとすると、一般的に発行部数*定価の8-10%が一般的とされているものの、出版社の方針とか著者との力関係でこのレートは変動する。さらに初版については出版社のコストが大きいこともあり、印税率は上記の半分程度まで下がるのが通例。
従って、初版の5,000部だけで終わってしまうと印税はせいぜい五十万円もらえれば御の字であり、原稿を作るのに3-4か月も費やす労力と比してみれば大赤字確定だ。
もっとも、事業主が出版する場合、印税収入よりも出版しているという事実自体に重要な意味があり、広告代わりという意味合いが強い。逆に広告代わりだと考えられないと労力にまったく見合わない結果になることは明白だ。
[headline style=”5″ align=”left” headline_tag=”h2″]参考:自費出版と商業出版
[/headline]
出版には大きく二つあります。商業出版と自費出版です。
後者は自分がお金払って作ってもらう本。業者はピンキリだが、ざっと100万円で100冊が目安と思えばいいです。
お値段は、文字だけの本か、フルカラーか、紙質はいいか、などでもかなり変わる。更にプラスして執筆を誰かに頼むならそのお代も必要。自費出版は全てを自分の好み通りにできます。
基本、書店に並ぶことはありませんがアマゾンのオンデマンド印刷出版(注文来た分だけ印刷して製本して送ってくれる)という方法を使うこともできます。
自分の本が出た、という実績作りとして広告効果を期待する人は少なくありません。
一般の方は自費出版なんて言葉は知りませんので、本を出してる人なんだ!と会社や商品の信頼性がグンと上がります。
工務店の社長が自然素材の健康に良い家を建てようという内容の本(半分くらいは自社の宣伝)を見込み客にプレゼントするというのはよくあるパターンです。
本を読んだうえで問合せしてくるようなお客様は成約率が極めて高く、特に工務店のような業態なら1人成約すれば利益が500万円くらいあるわけで、自費出版は住宅雑誌に広告を出すよりもめちゃくちゃ費用対効果の高い広告媒体になります。
似た例はたくさんあり、「ガンは治ります、この薬を飲めばね」とか、「美しい顔になります、私が手術すればね」という感じで高額の治療・商品・サービスを売る広告手段として、かなりコスパが高く、実際上、よく使われています。
他方、商業出版は出版社が製作費を払いますので自分のお金負担はほぼありません。
(とはいえ、執筆中は膨大な時間を無報酬で費やすことになります。今回の場合、すべて私が書いていますが、通常はライターを別途雇うことも多いので、その場合はこれが大きな自腹です。)
コネなしで企画書を郵送するのもアリですが、ふつうは編集者にコネのある人に依頼して出版社に企画書を見てもらい、首尾よく採用されたら出版に至ります。こっちは全国の書店に出ます。
商業出版では本に関する最終決定権は費用を負担する出版社にあるので、売れ行きに直結する可能性が高いタイトル・表紙デザインをどうするか、など重要事項は出版社の判断が最優先になります。
ここが理解できず、自分の意見を通したがる著者はよほど知名度がとあって本を出せば最低でも5万部は売れる、というような強力なファン層を抱えていない限り、総スカンを食い、出版界から姿を消します。商業出版ではあくまで自分の宣伝になる本を出版社の費用負担で出して頂く、ということを理解しておくことが必要です。
+-
[recent_posts style=”14″ rows=”three” title = “ビラボディ 人気の記事” text_excerpt=”Y” mode=”selectable_posts” posts_num=”” selectable_posts=”886, 951, 595, 1868, 3430, 1834″ text_color=”undefined” hide_author=”” ][/recent_posts]